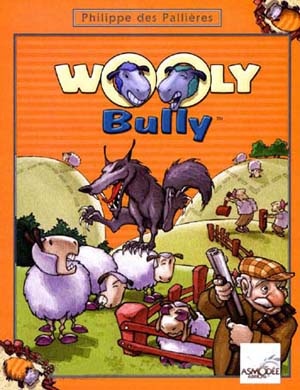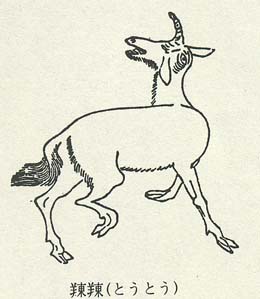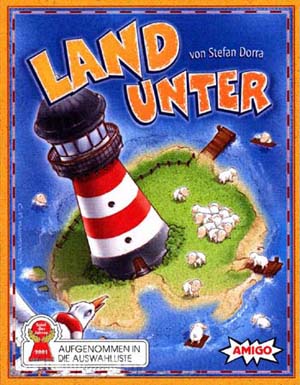そのころちょいちょい、ヴァージニア鉱山の野郎どもがぼくに向かって、おまえぜひジム・ブレーンって男に逢ってみろ、そして奴のおじいさんのおいぼれの頭突き羊の物語ってのを語ってもらえよ、そりゃ胸のわくわくする話だぜ、とよくそういったもんだ。
(略)
ぼくが席をみつけるが早いか、ブレーンがいった。
「思えば二度とあのころはこねえだろうな。あいつ、そりゃイカス頭突き羊だったな。あんなイカス羊が二度とこの世にいるもんか。おれのじじいが遠路イリノイから連れてきたんだけどよ―イエーツって野郎から分けてもらったんだ―ビル・イエーツってな―ほれ、おめえらもうわさには聞いてるだろう―奴のおやじは教会の幹事でよ―洗礼派ってとこよ―それから奴だって、大した働きもんでな。『感謝のイエーツ』といやあ、おめえ、奴に先手を打たれたくねえんだったら、朝もはよから起きていなくっちゃ追いつけねえって、というほどの働きもんよ。おれのじじいが西部に渡ってくるとき、グリーンの一家を口説いちゃって、いっしょに幌馬車を組んだがいいってすすめたのもこの野郎よ。そこであのセート・グリーンってのは、一族の花だったんじゃねえのかな。その嫁さんはウィルカソン―サラ・ウィルカソンてんだけどよ―これがまたええ子でな―
(以下ラスト近くまで略)
ジム・ブレーンはおもむろに、おもむろに、夢かまぼろし―首をこっくり、こっくり、一、二、三回やると―安らかに首うなだれ、とうとう、すやすやと眠ってしまった。野郎どもの頬から、涙がとめどもなく流れている―こみ上げる笑いをこらえようとして窒息しそうなんだ―
(略)
そのおじいさんの頭突き羊にどんな運命がふりかかったかは、今日にいたるもおぼろの神秘だ。それを突きとめたひとはまだいない。
マーク・トウェインの短篇小説、「頭突き羊の物語」です。つまり、主人公(と読者)はひっかけられたのですね。それは良いんですが(良いのか?)、なんで羊? そして頭突き?
ちなみに、この「頭突き羊の物語」について、筒井康隆がこのような分析をしています。
この短篇の独自性はその着想にある。現実にもしばしば起こるこの「話の横滑り」は、ギャグとしても比較的よく見聞するものだが、これを最後まで横滑りしたままで終らせ、読者の願望不充足をも笑いに換え、それを一篇の短篇小説に仕立てあげようとは、それまで誰も思わなかったに違いないのである。
そうなのかもしれないけど・・・そうなんだろうけど・・・この不充足をどこに持ち込めば良いのか。なぜ羊ー!