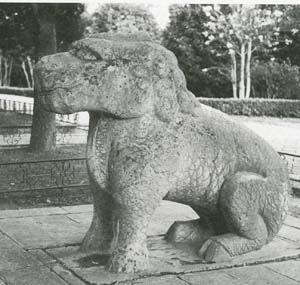近世中華より来たが、まだ蕃息(はんしょく)していない。その状は、頭・身相等しく、毛は短い。惟一両(ひとつがい)だけが公家で牧われ、これが数十頭になっている。それ故、人もこれを食べることは希である。
儘これを食べた者の謂うに、「肉は軟らかく味は美い。能く虚を補う」というが、予は食べていないので、その主治については詳らかでない。
牧家が戯れに紙を与えれば、羊は喜んで紙を食べる。然ども、これは常の食物ではなくて、たわむれに食べるだけなのである。
「本朝食鑑」は、江戸元禄期における食品学の集大成です。獣畜部には羊の項目もあるのですが、食べ物としての羊の話であるにもかかわらず、やっぱり紙を食べるとの記述が。江戸の羊って・・・。