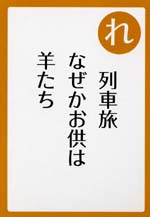半ば植物、半ば羊というこの存在は「ボナレッツ」とか「ボラメッツ」と呼ばれて、プロテスタント詩人ギヨーム・サリュスト・デュ・バルタスによって文学の分野に導入される。
(略)
根は臍につながっていて、周りに伸びる草を喰ってしまった
その日のうちに死んでしまうのだ。
ああ、神の右手の驚嘆すべき成果よ!
植物が肉と血をもち、動物が根をもつ。
(略)
(デュ・バルタス『第二聖週間』「第一日、第一巻、エデンの園」、第515―524行)
デュ・バルタスが1578年に『聖週間あるいは世界の創造』を上梓してから、1581年にはプロテスタント牧師シモン・グーラールの厖大な註釈付きで改訂版が出版されるなどして、このおよそ6500行におよぶ長編詩は大きな成功を収めたのだった。
(略)
それの続編として1584年に出版されたのが右に引用した『第二聖週間』であり、これについてもグーラールは1589年に詳しい註釈を世に送ったし、デュ・バルタスの死後一年経った1591年には言語学者クロード・デュレも『第二聖週間』の「エデンの園」の巻だけの註釈を発表した。
そのグーラールがデュ・バルタス言うところのボナレッツを説明するに際して、その典拠を明らかにしている。
それは1549年にウィーンでフェルディナント皇帝に献呈されたジークムント・フライヘル・フォン・ヘルバーシュタインの『モスクワ公国事情解説』である。
(略)
この植物動物には血があって肉は皆無である。
でも肉の代わりになにかしらザリガニの身に似たものを具えている。
(略)
その根は臍ないし腹の中央についている。
自分の周りにある草を喰い、草が続くかぎり生きている。
(略)
『第二聖週間』の註釈を公刊したクロード・デュレも『驚嘆すべき植物草本の驚異譚』(1605)の第29章でヘルバーシュタインの伝える話を採り上げながら、マンデヴィルやスカリジェールやカルダーノやギヨーム・ポステルなどが「ボラメッツ」について触れたと指摘している。
伊藤進「怪物のルネサンス」から、植物羊の解説を引いてみました。
植物羊には、オドリコ 「東洋旅行記」やマンデヴィル「東方旅行記」のような羊が莢に入っているものと、ヘルバーシュタインやデュ・バルタスやクロード・デュレの言う臍からのびた茎で地面につながっているものの二種類があるようです。こちらでご確認ください。左がマンデヴィル「東方旅行記」、右がクロード・デュレ「驚嘆すべき植物草本の驚異譚」からのものです。
あと、関係があるのかないのか、たぶん無いと思うんですが、「本草綱目」の地生羊は、臍でつながってるようですね。